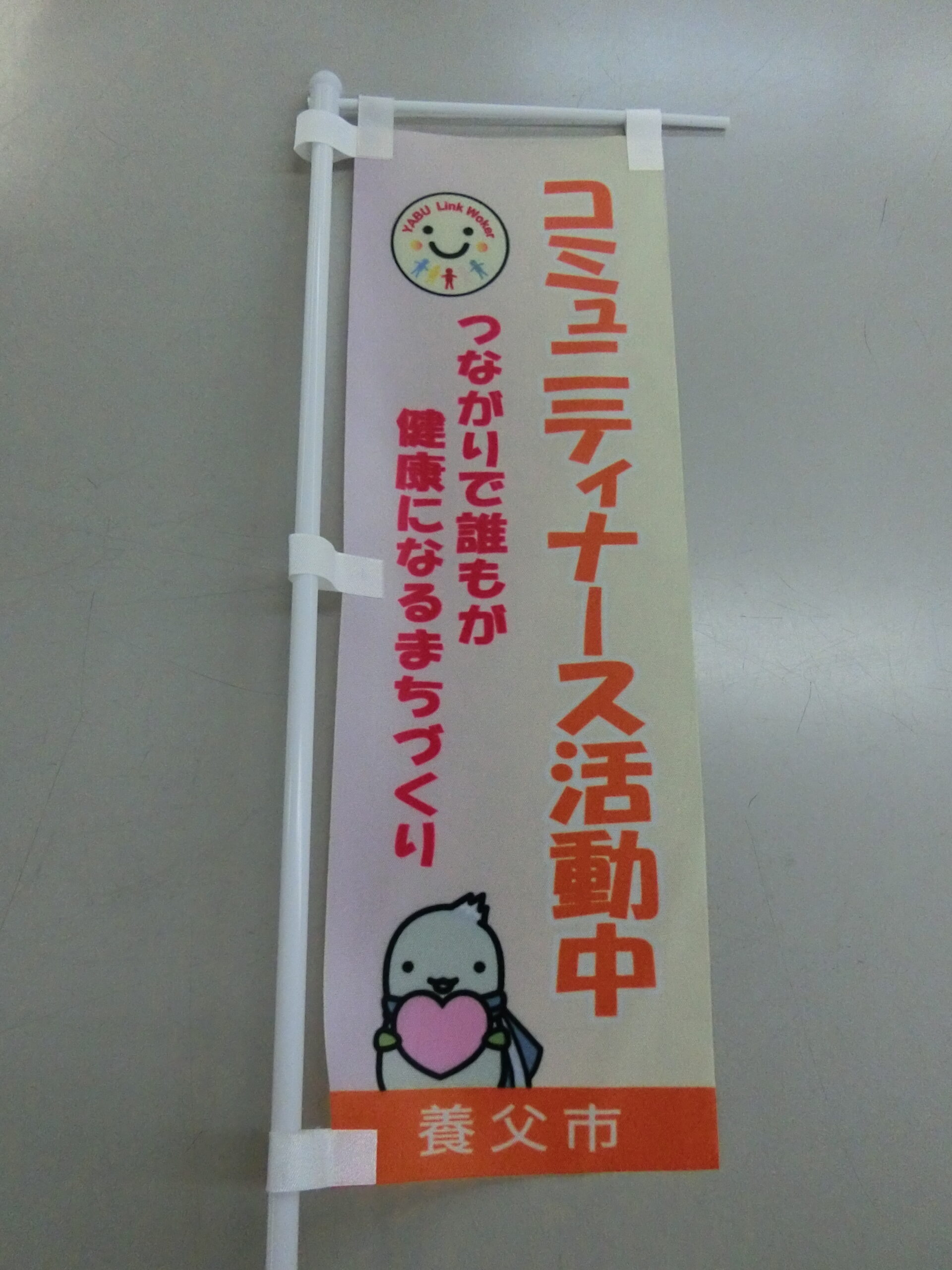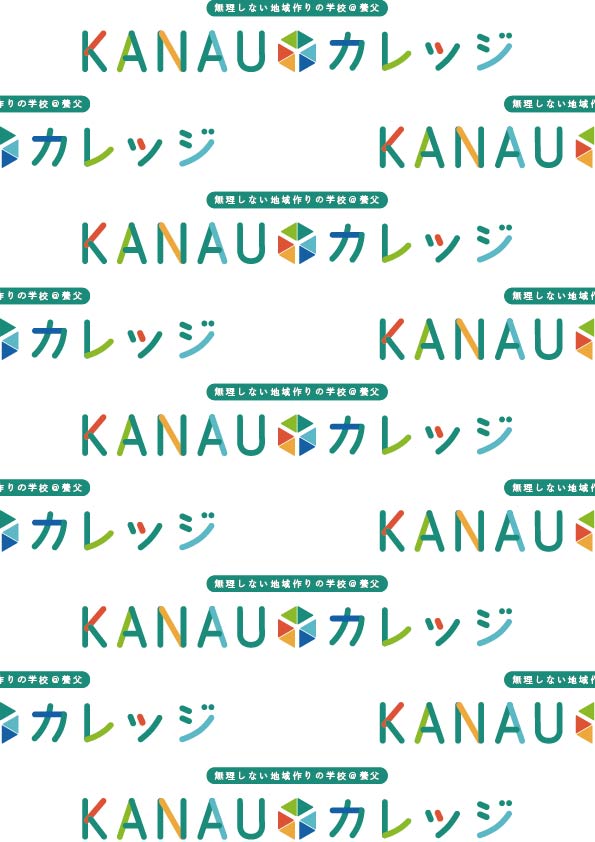- その他
- 養父市全域
- 全ての世代
- その他
用事がないと来たらあかん場所じゃなく、用事がなくても来てもら う場所に。〈建屋校区自治協議会 藤原さん、谷野さん〉- やぶひと Vol.03
ライターの伊木(いき)です。
社会的処方推進課の皆さんと一緒に、2023 年 8 月からお仕事をしています。その中で 養父市内を中心にさまざまな活動をしている人たちにお話を伺っていて、すごく魅力的 な人がたくさんいることに気付かされました。この記事は個人的な視点で、地域内の活 動を「人」にフォーカスしてご紹介するシリーズです。
👇このシリーズの他の記事はこちら
新聞をコミュニケーションツールにする新聞屋〈長島敏行さん〉- やぶひと Vol.01
職場を明るく楽しい場所に変えたい!〈尾山さん〉- やぶひと Vol.02
今回は建屋校区自治協議会、事務局⻑の藤原さんと事務員の谷野さんにインタビューを させてもらいました。
建屋校区自治協議会では、コミュニティバス「タッキー号」、軽飲食を提供する「ふれ あい喫茶」、様々な商品を販売する「ミニミニコンビニ」、大人が学ぶ教室「たきのや大 人の学校」、移動販売の受け入れ、小学校との連携等、さまざまな取り組みを実施され ています。その核となっているお二人に話を聞きました。
自治協議会がコンビニをやってる?

伊木:隣で小学校から声が聞こえるのがすごく良いですね。
谷野:いいんですよ。すごく幸せな環境ですね。
藤原:今は授業の時間ですが、昼休みの時間は小学生がたくさん出て来てね。建屋小学 校は今、1 年生から 6 年生までの全員で 50 名もいません。特認校なので生徒は広谷な ど、市内各地から来ています。昼休みは結構大きな声でみんな遊んで、先生も出てきて 一緒にサッカーやったり、ボール投げやったり、追っかけられたりしてるから。もう本 当に賑やかです。
谷野:運動会の練習の時とか面白いね。教頭先生や校⻑先生も手を振ってくれるんです よ。
伊木:それぐらいの距離感ですよね。すぐそこは運動場で、小学生もこちら(自治協の 建物に)にすぐに来られるくらい。
谷野:見学に来ることもあるし、学校が早く終わった日にはお菓子を買いにも来ます。 他にそんな場所がないからね、自転車でお菓子を買いに来て自治協の中で食べたりとか、 ジュース買って飲んだり。「カップラーメンにお湯を入れて」と言われることもあって、 藤原局⻑が「僕が入れたろう」って入れてあげて。最後には「ちゃんとゴミも片付けよ うね」言うて。そこら辺の指導までして。昔からある、近所の人に教えてもらうような 感じで。中学生も来ますよ。
伊木:この辺りの一番近い中学校は養父中学校ですよね。
谷野:そう。バスで帰ってきて、家で自転車に乗りかえて来てくれます。自治協で facebook を更新してるんですけど、中学生がフォローしてくれていて「明日行きたいん ですけど、開いてますか?」「ごめんなさい、明日は閉めています」とか、そんなのをや り取りしてるんですよ。
伊木:ミニミニコンビニされるまでは、この地域にこういうものが買える場所ってあっ たんですか。
藤原:なかったんですよ。もう 4 年ぐらい前かな、コロナ前から閉めちゃってたからね。
谷野:子どもがそうやって集まったり、食べ物が買えるような商店は全部閉めていっち ゃってて。私が子どもの頃、私の実家が三谷地域で商店をしてたのもあって、これ(ミ ニミニコンビニ)をやろうかなと思ったんです。皆が集まった時に「コンビニが欲しい」 という話が出るんですよ。そんなの早速は無理だし、区⻑さんたちが「ここ(自治協の 建物)で何かできたらいいけどな」と言ってて。私もちっちゃい頃から見てるから、お 店屋さんの真似事やったらできるかなと思って。それで買い出しに行って、最初は”まつ べた”4つくらいかな。ちょっとだけ並べてみたら、結構売れたんですよ。そしたら今 みたいに広がっていって、ラーメンやレトルトカレーを置いて。最終的にはアイスクリ ームまで置き始めたんで、市の補助金(養父市持続可能な地域づくり事業補助金)を活 用して冷凍庫と冷蔵庫を準備しました。
藤原:(補助金で備品を購入したのは)令和 5 年度でしたね。ジュースを冷やす冷蔵庫 とアイスの冷蔵庫。
谷野:ノボリ旗もそうですね。それまでは手作りのもので賄ってました。奥の冷蔵庫に 冷やしていたものを、お客さんが来たら「どれにする?」言うて見せて。ほんでまた戻 すみたいな感じで。ほんまの手作りのお店だったんですよ。まねごとみたいな。
伊木:それはいつ頃から始められたんですか。 藤原:令和4年ですね。
谷野:多分 1 年ぐらいそれをしたんよね。その後に補助金の募集をしてるのを知って、 局⻑と「ほんなら、それで機材を充実させたらいいんかな」言うて。そしたらよいしょ、 よいしょってアイスを運ぶ手間も省けるし、入ってすぐそこにジュースが置いてあって 買えるようになるので。それから買い物もクーラーボックスやカゴを買ってもらったの で、便利がよくなりました。ミニミニコンビニをしてみて、良かったらミニコンビニに なって、最後はコンビニが呼べたらいいなっていうのがあるんですよ。だからわざわざ 2 回もミニを付けたんです。名前が変わって進化していくんですよ。最終的にはコンビ ニが呼べたらいいなという夢を持ちつつ、それまでの間のミニミニコンビニ、ミニコン ビニを目指してるんです。
藤原:建屋と三谷の自治協とね。合計10区で組織している建屋地域活性化対策委員会 というものがあります。そこでも「バイパス沿いにとにかく拠点を作りたい」という話 がもう何年も前から出ていて、土地は一応確保しています。もし拠点をこれから先作れ るとしたら、そこではミニミニコンビニから今度コンビニぐらいになって、ちょんまげ
寿司もそこで売るとかね。そういう地域の人が集まれる、地域を通っていく人がそこで 集まれるような、そんな場所にしたいなっていうことが今の建屋地域の夢なんです。
谷野:これがダメやったら次はこれ!って、夢がどんどん浮かんでくるんですよ。
小学校と連携して、新しい文化教室にチャレンジする『たきのや大 人の学校』
藤原:最終的にはこのミニミニコンビニもそうですし、移動販売であったり、令和 6 年 度は同じ補助金を活用して『たきのや大人の学校』という地域の大人が集まっていろん なことをやるような教室をやってます。もちろんタッキー号もそうです。「自治協って何 をするところなんだろう」って谷野さんと僕も話をしていて、やっぱり困ってる人が多 いんじゃないかという話になります。買い物に行くにも家からバス停までが遠いから送 り迎えをしたり、日常の食料品なんかを買う機会として移動販売をやってもらったりし てるんです。こういうことで困ってる人を何とか少しでも助けられたらいいんじゃない かっていうのが、これからの自治協というか、地域活動をする中の大事なとこかなと思 うし、そんな取り組み全てが〈社会的処方〉の一環じゃないかと思ってるんですけどね。
谷野:ここを使った文化教室も今は 3 つぐらいしか残ってなくて、参加者も少ないよう な状態で課題だったんです。でもドコモさんを呼んで、スマホ教室をしてみたんです。 そしたら 10 人ぐらい来られるんですよ。普通の教室だと 3 人とか 5 人ぐらいまでしか 来ないのに。最初は文字を打つところから「キーボードってどうなんやろう」「カタカ ナに変えるのどうするの?」ぐらいのところから始めて。何回か続けるうちに、大勢が ずっと通ってくれるようになって。
藤原:去年は 7 回、今年度はすでに 2 回やりました。
谷野:局⻑が補助金の申請をしたっていう時に、新しいことやったら来てくれるかなと。 ずーっと同じことしかしなかったら人が出てこなくなる。だからいろんなメニューを入 れてみて、新しいことをポンポンポンポン入れたら食いついてくれへんかなと思って考 えてみたんです。老人大学(但馬⻑寿の郷 健康福祉大学 とが山学園)ってありますけ ど、そこまではちょっと遠いでしょう。でもここなら車に乗らない人でもタッキー号が あるから来れるし「大人の学校いいんちゃうかな」って。実は違う内容で補助金申請を 出しかけとったんだけど、プレゼン前日ぐらいに「私、実はこういうのがしたかったん
です」って局⻑に言ったら「一回それ書いてみ」って言われて。それを目の前で走り書 きで書いてね。ほんなら局⻑が「ええやないか、これを明日言おう」って言ってくれて。 小学校も絡めたらどうやろうってなったんです。局⻑は小学校の運営委員もしているの で、小学校とも掛け合ったら校舎を使わせてもらうことになって。先日、実際に小学校 で生徒と一緒に社会とか理科の授業を受けました。自治協だけじゃなくて小学校でスマ ホ教室をしてみたり。他にも私が授業をやってみたりとか。算数のドリルぐらいの簡単 なやつをして、みんなでワッハッハって笑って。みんなも内容が分かったら「また人呼 ぶわ」いう感じで参加者がパーッと増えたりとかして、すごいありがたいことに好評だ ったんです。そして最後は食べ物で釣るって決めてて。1 個でも教室に来てくれた人は、 給食を一緒に食べれると。ちょんまげ寿司のところでお弁当を作ってもらって、それを みんなで食べましょうよって、最後にわいわい食べて。ジャンケンゲームをやって盛り 上がって。それで前期は終わって、後期はまた違う人がちょっと来はじめました。当初 80 代〜90 代の人が多かったのが、70 代前後の人も来てくれるようになったんです。ち ょっといい感じだなと思ってます。
藤原:前期が終わってアンケートをとったら「続けてほしい」とか「これをやってほし い」とかっていうものがあったんで、そういうのも入れながら、ちょうどやってるとこ なんですけどね。少なくても 8 名、多いものは 15 名ぐらいは来てますね。しまんと新 聞バック作りは好評でしたね。前期の時に小学校の児童と一緒に社会や理科の授業をや ったんですよ。地域の参加者も「なかなか楽しかったわ」って言ってくれて。新聞にも 小学生と一緒に勉強してることを掲載してもらいました。
谷野:「初めて小学校に来た」っていう人もいました。「孫がおらんと行かれへん。敷居 も高いし」っておっしゃられてて。あと英語の授業を大人だけでやったんですけど、今 までも小学校が地域の人と英語の先生と一緒に英語教室をやってても、人がなかなか来 ないんですよ。英語って難しいと思って。でも大人の学校でやった授業はみんなで楽し くできたんで、上手に導入できて良かったんじゃないかなと思って。
藤原:今まであまり出て来これなかった、来にくかったような人とかね。そういう方に も何とか来てもらって、閉じこもるんじゃなくて、出てきてしゃべってもらうことには 効果が出たんじゃないかなと思います。もちろんコンビニもふれあい喫茶もそうですし、 人が結構ここに集まってきてくれてるんです。
自治協ってどんなところだろう

谷野:自治協ってね、役員さんが会議に行く所みたいなイメージで、他の若い人たちは 「自治協ってどこにあるの?」とか何をしてるのかが分かってなくて。私が来た 7 年半 前は、ここに来ても誰とも会わずに帰る。ただ事務仕事だけして帰るっていうような場 所だったんですよ。時々区⻑さんが来て会議をする、そんなんやったんですけど、そう じゃなく、いろんなことをするようになったら皆さんが「ああ懐かしいわ〜。昔、⺠生 委員で会議しに来てた」とかね。そんなことを言ってくれるような人達がまた来てくれ たり、子供たちが自転車で来てくれたりとか、若い世代が夏休みにラーメンを買いに来 てくれたり。そしたら最近は特認校で来てる少し遠くに住んでる子がここで買い物をし て、迎えに来た車に乗って帰ることもあって。何かいい具合で使ってもらえてるような 気がして。品数とか多くないんですけど。私が子供の頃に実家の商店にあった風景がま た見れて、すごい嬉しいなと思って。最初すごい感動しちゃって。小学校から社会見学 に来られるときに、先生が児童に 100 円を持って来させるんです。見学をしたら最後に 「お菓子買って良いよ」って、お金と商品を交換して帰るっていう買い物体験がこの建 屋地域でもできるっていうのがすごく良いなと思って。年配の方も仏壇のお供物を買っ てもらってるし。やっぱりアイスクリームを食べれるのが一番大きいね。
藤原:年配の方はバスで買い物に出てる人がほとんどじゃないですか。そういう人は絶 対にアイスは溶けるので買えないんです。けど、ここだと買ってタッキー号に乗って家 まで帰ることができるから。
谷野:わざわざ一回バスから降りて、ほんでここで買い物してからタッキー号で送って。 子供だけじゃなく大人も目をキラキラさせてます。メカブってあるでしょう、おつまみ の。あれが爆流行りした時がありました。流行ったら一人で 10 個ぐらい買っていく人
がいるんですよ。「これ買って食べたらおいしかったで」とか、それも会話の一つで情 報交換にもなる。何ならここで開けて食べるしね。「コーヒー頼むから、私これ買って ここで広げるわ」って。すごい生き生きして、おばあちゃんたちが何か子供みたいな笑 顔になるその瞬間もまたかわいいですよね。
伊木:普段はあまり出てこない人がこういうところに出てくるようになったというのは、 何がきっかけだったんでしょうね。
藤原:タッキー号もありますね。車を持っていない人は結構いるんで、そういう人は谷 野さんが迎えに行ったりして、ここに連れてきてまた 1 時間、2 時間して帰ると。それ だけじゃなくて、3B 体操や教室の時の送り迎えや病院に行く際の家からバス停までの 送迎もやります。そうなると動きやすくなるんですね。もちろん大人の学校なんかも影 響していると思います。
谷野:結局用事がないと来たらダメな場所と思い込み過ぎてる。だって用事がないのに 市役所に行ったりしてないでしょ。自治協もそうなっちゃったんですよ。だから用事が ないと来たらあかん場所じゃなく、用事がなくても来てもらう場所にせんとだめだなと 思って。それで『ふれあい喫茶』ってね、ここに来たら 100 円でコーヒーとお菓子は出 すから、いつまで居てもらってもいいよとか。あとお菓子を買いに来るとか、ジュース を買いに行くというような、あえて用事を作ってあげたんじゃないですけど、用事がな いと来たらダメ。という頭をなくすことが大事やし。だから私らも最初のうちはここの 前を歩いてる人を見つけたら「中に入りんせぇな」って声掛けしてたんです。タッキー 号で出かけたときにも「最近来てないやん。また来てよ」とか言ったり。そしたら顔を 見に寄ってくれたり、野菜を持ってきてくれたり、それを口実に来てるのかもしれない ですよ。「これあげるわ」で来れる用事ができてるじゃないですか。だから仲良くなる ことによって野菜をあげたいとか、野菜を持っていったらここには入ってこれる。何か 用事を作ってでも来てくれるようになったりとか、パイプをいっぱい持ってたら来ても らえるし、スマホ教室をすることによって、これがどうしても分かれへんから言うて、 ここはドコモじゃないのに私がドコモに電話して取り次いで。「スマホが分からへんか ら自治協行こう」「お菓子欲しいから自治協行こう」っていう簡単な用事を済ませられ る場所になったらいいなって。結局手探りなんやけど「とにかく来て」っていうような 感じで。その代わり、来たら私らも面倒くさそうにしない。局⻑との決まりが「その時 は仕事の手を止めてしゃべる」というのを話してました。事務仕事は全然進まないです けどね。局⻑が OK って言ってるんやから、2 時間でも 3 時間でも私はしゃべって、ま た来ようって思ってもらえるように仕向けていったっていうのも大きいやんね。
対話や会話でつながる地域

藤原:僕はそれが本来の自治協の仕事だと思ってるんですよ。机に座って事務処理をし とるだけじゃなくて、来た人と話をするとか情報交換したりとかね。そういうようなこ とをやるのが自治協の仕事かなと。救急車やドクターヘリが来たら「あれは誰だった?」 というのも情報として必要だし。あの人は大丈夫かな、元気にしとるかなとかね。本来 の仕事っていうのは、僕はそれじゃないかなと思ってね。
谷野:だからもういつも来てくれてる人がちょっと来なくなって、1 週間見かけなかっ たらやっぱり心配ですもんね。だから見守りも兼ねてるっていう意識を持ってて。しば らく来てないなと思ったら、近所の人が来た時に「あの人最近どう?」って聞いて「病 院に行きよんなったで」「そんなら生きとんやな。OKOK」って。そういうのも会話の 一つとして気にかけるのも大事かなと思って。やっぱこういうとこ来て、ずっとパソコ ン向かってカタカタしながら対応されたら感じ悪いし、忙しそうだから帰ろって思う。
藤原:ほんとの自治協の仕事をちゃんと対話とかね、会話で全部やれてるからいいなと 思って。それも全て社会的処方に繋がりますよね。
伊木:意識してないけど、いつの間にかその活動が社会的処方になってますよね。
藤原:意識してないですね。タッキー号で迎えに来てって言うたら、とにかくいつでも すぐに行くでって言うて迎えに行ってあげたりとかね。このミニミニコンビニも地域の
人も大助かりで集まってくる。今日もライオンカフェをやってましたけど、17 人来たっ て言ってました。集まった人たちが楽しくワイワイと喋れるのを見てて、こっちも良か ったなと思う。あとマックスバリュが毎週火曜日に移動販売に来てるんですけど、10 時 半ぐらいにここで店を開く。
谷野:それも話が来た時に私が「絶対やるんや」って。
藤原:「絶対に火曜日にせぇ」って谷野さんが言うんです。僕はあんまりよく知らなかっ たけど、火曜日は火曜市って安くなる日なんです。
谷野:店舗とおなじ金額なので。だから説明を受けてすぐに「他に誰か申し込んでおら れますか?」って聞いて「これは説明の段階なんで、誰もまだ考えますって言っておら れる」って言うから「私やります。もう申し込みます」って。「火曜日じゃないと嫌です」 って言って、火曜日に手を挙げたんですよ。
藤原:今は結構ね、レジ前に並ぶくらい来られてます。早い人は朝 9 時ぐらいに来てね。 火曜日はグランドゴルフの練習をやってるので、そのメンバーが 10 時から 10 時半ぐ らいに来て、ここでコーヒーを飲んで話して。
谷野:だから目当ては買い物じゃないんですよね。買い物には困ってなくても来てる人 もいる。ここに来たら人に会えるから。だから買い物までの時間潰しでふれあい喫茶で コーヒー頼んだりお菓子食べたりってして。みんなでしゃべるのが楽しみで、早くから 来るんですよ。なんなら私より先に来る。「あんたの手を止めて悪いな」とか言いなが ら、もうずーっとしゃべって。「最近面白い話ない?」とか言ったら、昔の話を聞かせ てくれたりね。お見合いした話とか、もう九十何歳の人がそんな話をしてくれたり。
伊木:移動販売もここに来る理由を作るっていうことの一つなんですね。今日はいろん な話を聞かせてもらってありがとうございました。
谷野・藤原:ありがとうございました。